推薦のお言葉
専門家からのコメント
Recommend from Experts

小貫 睦巳 様
常葉大学保健医学部理学療法学科 准教授
このような仮想現実ゲームは、これから「生体センシング技術」がさらに良くなることで無限の可能性がある分野です。これからの介護予防に欠かせない運動機能・プログラムとなっていくことでしょう。

辻下 守弘 様
奈良学園大学保健医療学部リハビリテーション学科 教授
リハビリテーションは、心身に負担のかかるトレーニングを地道に行う必要があるため、患者さんが「つらい」と感じてしまいがちです。こうしたリハビリの現状を大きく変える可能性を持っているのが「バーチャル・リハビリテーション」という新しい技術であり、その一つが「TANO」なのです。

逢坂 大輔 様
株式会社シーエフロボタス 代表取締役
理学療法士
TANOはセンサーを活用した新しいリハビリ&レクリエーションシステムです。 各専門家によって監修された発声・運動・脳トレといった効果的なプログラムは、子どもからお年寄りまであらゆる年代の方にとって必要な要素を備えており、ゲーム性を併せ持った内容により、知らず知らずのうちに効果的な運動を行うことができます。

川守田 拓志 様
北里大学医療衛生学部視覚機能療法学 准教授
TANOは手と目の共同運動をはじめ五感を駆使し、仮想現実と楽しい教育を融合した 新しい可能性を開くコンテンツと思います。

田中 一秀 様
通所介護・介護予防 フィジオルーム見附町 施設長
理学療法士
リハビリテーションにおいて、心身機能の向上は必須でもあります。使用方法も過度な説明を必要とせずに直感で操作できることも自由度が高く、健康維持、自主トレーニングなど幅広く活用する事ができます。

沢井 加織 様
特定非営利活動法人いちご /デイサービス いちご/リハロボセンター 向日葵
理学療法士
リハビリテーションと聞くと、「しんどいもの」「つらいもの」と思われますが、このTANOは機能訓練を「楽しいもの」に代えてくれるリハビリテーション道具です。利用者様同士で盛り上がりながら、運動や脳トレ・発声練習ができます。デイサービスや施設では日々の日課やレクリエーション項目に悩みがちですが、このTANOが一台あるだけで、どのような使い方でもできてしまいます。
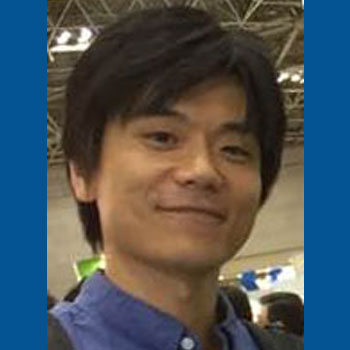
近藤 勇太 様
理学療法士
知らず知らずのうちに効果的な運動が自然と身についてしまうのが「TANO」の魅力。 リハビリテーションには運動トレーニングが重要です。 入院中は環境を用意する事で指導できますが、退院後も継続するのは大変な事ですが、 TANOは、「今日も遊びたい」「悔しい、もう一回」と運動を継続したくなる画期的なツールだと思います。

王 玉 様
沈$9633$79EF水潭医院 主任医師
新しいアイディアと方法で子供たちに新しい喜びをもたらし、トレーニングプロセスに楽しさと好奇心を生み出しました。子供たちは順番に協力してより効果的なリハビリテーションを行うことができるシステムです。

安達 栄次郎 様
北里大学名誉教授 医学博士
初めてTANOゲームを知ったとき、これはゲームソフトウエアでありながらリハビリテーションにも運動機能評価にも使えるツールであると直感しました。ゲームを楽しみながら知らず知らずのうちにリハビリテーションメニューをこなしてしまう、そして検査されているという緊張感なしに運動機能を評価されている、そんな使い方をしています。

岸本 好弘 様
日本ゲーミフィケーション協会 代表理事
実際に10数種類のゲームを体験しましたが、どれも1-2分で終わるミニゲームなのですが、分かり易くて操作しやすい。運動・発声・脳活性化トレーニングが楽しめました。 元ゲームクリエイターとして思ったのが、Kinectのカメラセンサー、音声センサーをうまく使って、多彩なアイデアでシンプルだけど面白いゲームを開発している所がすばらしい。
感想の声
高齢化が進む中、社会保障費の増大が著しい社会情勢において自助・互助の促進は必須課題であると思われます。今回推薦させていただくTANOは、その自助・互助を促進するために非常に有用なシステムです。
TANOのコンセプトにもある「楽しむ」ことをしながら自然と体を動かしたり、声を出したりすることが出来るので、利用者の方から「楽しい」「もっとやりたい」という声が多く聞かれています。
特別なコントローラーなど使用せず、シンプルなシステムが多いため、介護職員の関りが少なくても使うことができます。「利用者が自分達の力で、楽しむことができる」というのは、今後の超高齢化社会においても新たなシステムの形として非常に魅力的だと思います。
ペッパーや介助用ロボットは施設で導入したが、楽しむジャンルのロボットは新規的だ。
本来のリハビリメニューにつなげていくツールとして、「ここに来れば楽しい」とのきっかけとなる、簡易リハビリや楽しみの提供になればと考え、モニターを希望。モニターは認知症で物忘れがあり、毎回「TANO」の記憶はないが、「こんなの初めて」と新鮮な気持ちで楽しみ、一方で体はコツを覚え、プログラムの得点が回を増すごとに上昇した。実施中、画面風景からモニターの思い出話も広がった。意外な一面を知り、施設スタッフとモニターの親近感も増した。操作側も楽しみ、その名の通り、「TANO(楽)」しさ最上級であった。初回はモニターの声も小さかったが、終盤には発声プログラムで大きな声を出し、他者を応援する等、モニター間の連帯感も高まった。操作そのものは簡単なので、今後タッチパネルを連携させれば、利用者がプログラムを選択し、自立操作していくことも可能かもしれない。
患者にとって目安になり、また動機付けにもなり有効である。
入院・外来、年齢、身体の麻痺の程度、コミュニケーション障害の種類のいずれによらず、使用者 の適応範囲は広くあると考えられた。特に視覚的に患者が発した声がモニターできる点は、患者にとって目安になり、また動機付けにもなり有効である。
プログラムはとても面白そう。老健施設入所中から、退所後にデイケアで継続していく等の使用も想定できる。在宅で個人が利用する場合には、個人で目標設定し、モチベーションを維持する作りこみが必要になる。またネットワーク回線で誰かとつながっている環境を作る事がリハビリテーションの継続に求められる。地域でコミュニティを作るとか、イベントを行う等の取り組みに発停していくのかもしれない。これにより、地域で引きこもりや自殺者が減少するような効果も期待できれば良い。被災地や認知症向けの利用も可能性があるのではないか。
ゲーム感覚でのレクリエーションを好む高齢者や障害のある方などの身体機能の活性化や脳の活性化が図れる点と子供と一緒に楽しむことができることから多世代での関係を構築していくことで自立した生活につながると期待できる製品として評価できます。モニター評価時には「頭の回転が良くなりそう」「楽しみながら脳を使うことや身体を動かすことができた」といった声や、介護者からは「体が脳を動かすきっかけとなりうる」といった声が寄せられました
コントローラーなどを一切使わないことから、歩行が困難な車椅子の方や寝たきりの方でも運動の疑似体験ができ、また、声に反応した遊びを提供することで普段は大声を出す機会の少ない高齢者に自然と発声する機会を与えることができる。
様々なコンテンツにより、誰でも簡単に、大勢で、楽しく続けられる製品となっている。介護スタッフが行うレクリエーションの要素をコンテンツに盛り込むことにより、介護現場における人件費削減とスタッフの労力を軽減することができる。
明確なコンセプトを持って開発されており、ソフトの拡張性と現場サイドの声を充分に反映した相互コミュニケーションツールとしての有効性が高く評価された
- 市販のゲームに近くて、大勢の子供が夢中でした。
- とても楽しそうに参加していたから(大人も楽しめました)
- 期待通りのソフトのバリエーションだったが、専属に職員をつけなければ使用できないので、人が割けない体制の中では使用が難しい。
- 楽しめそう。簡単。
- 楽しく体を動かせる。
- なかなか運動のできないお年寄りなどにいいと思いました。
- 施設などでしっかりされた方は、頭や体の体操になっていいとおもいます。。
- 数の入り方がわからないが、運動になりいいと思う。
- 大勢で楽しめて家族でできるので、コミュニケーションが取れていいと思いました。
- リハビリしましょう、動きましょう、では動けないがゲーム感覚でできてOK。
- 利用者さんサイドで楽しく利用できそうです。軽い頭の体操には最適と思う。
- ちょっと高齢者には難しいと思う。
- 脳トレと手の動きを楽しみながらできそうです。
- ホーム等でコミュニケーションに利用できる。
- 頭の体操になっていると思う。
- 車いすの方なども楽しんで体を動かせると思います。
- 一人から数人で楽しめる。
- 毎日同じ体操では飽きるので体を動かすにはいいかな。
- 理解しやすそうなゲームもあり試したい。
- 声や体の認識を何らかのアタッチメントが不要で便利。
- 機械の体験者を認識する能力がいまいちでした。
- 価格が妥当なら大人数で楽しめる。
- 個人~複数単位で楽しめると思いました。
- 自分の動きが反応してわかるのでいいと思いました。
- 認知症の利用者様も集中して参加していたのでいいと思った。